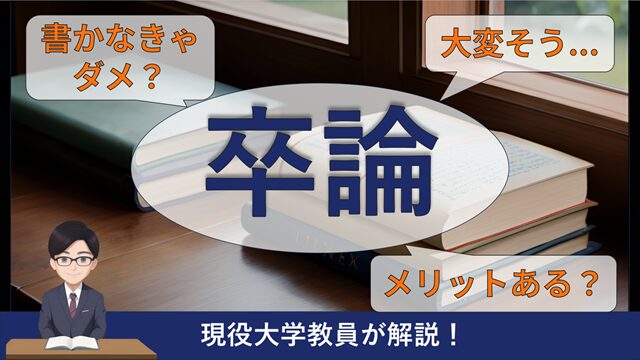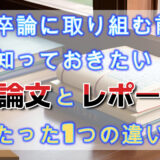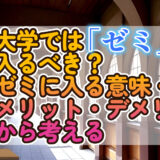・卒業論文はどんなのもなのか。
・卒業論文は書いた方がいいのか。
・卒業論文を書くメリット・デメリットは何か。

現役大学教員(私立大学,経済学部)
学生と接する中で伝えたいたくさんのことをブログ(サードゼミブログ)で発信中。
毎年学生ごとに異なるテーマでのゼミ論・卒論指導をしている。

卒論って書いた方がいいの?意味あるの?
就職も決まったし,書かなくてもよくない?
卒論を書かずに卒業する友達もいるけど,自分はどうしよう…
こんなふうに悩んでいる学生も多いと思います。
卒論が必須の大学であれば選択の余地はありませんが,卒論が必須ではない大学・学部の場合はどうでしょうか?
私の所属大学・学部では卒論は必須ではないので,毎年のように,「4年のゼミ(=卒論を書く)は取らないといけないんですか?」と聞かれます。
学生としては,「就活もあるし大変そう」と考えてのことかもしれませんが,そのたびに伝えている私の意見は,

卒論はぜひ書いてみて下さい!
です。
卒論を書き上げると,長い文章を論理的に書く力,長期間の計画を立てて「答えの分からないこと」に取り組む力を付ける貴重な機会になりますし,長い論文を自分でまとめたという自信と達成感も得られます。
この記事では,卒論を書くメリットについて解説しながら,「卒論を書こうか迷っている」という学生の悩みを解決します。
卒論を書くメリットとデメリットが分かれば,モチベーションも維持しやすくなるはずです。
1.卒論とは何か?

そもそも,卒論って何?
卒論=卒業論文は,4年次に書く(基本的にはゼミの中でやることが多いでしょう)論文のことです。
論文に限定した卒業制作といった感じです。
2年次や3年次にも「ゼミ論=ゼミ論文」を書かせる大学・学部・ゼミもありますが,ざっくり言ってしまえばその4年生バージョンです。
レポートとゼミ論・卒論の違いについてはこちら⬇️の記事にまとめてありますので,よろしければご覧ください。
大学では,主にゼミの活動の中で,自分の決めたテーマの研究に取り組みます。
卒論はその集大成という感じです。
集大成ですから,求められる水準もそれなりに高いものになってきて,たとえば,
- その分野についての基本的なことを勉強して,理解した上で書いていること。
- 論理的な文章で明確に書かれていること。
(感想や感情ではなく,読み手に正確に主張が伝わるように書かれていること。) - 新しい知見,独自の主張がされていること。
(ただ調べてまとめただけでは論文になりません。)
が求められます。
「勉強」ではインプットすること(理解すること,覚えること)が重視されます。
「研究」では,そのインプットを上手く使って,自分で課題を設定する→自分で検証する→自分で文章にまとめるという,「アウトプット」が重要になります。
2.卒論はできれば書いた方がいい
この記事の本題である「卒論は書いた方がいいのか?」ですが,結論から言えば,
書いた方がいい
です。

資格試験の勉強をしていてそれどころじゃないよ!
とか,

自分で起業していてそれどころじゃないよ!
というように,「卒論よりも大事なことに取り組んでいる」場合には,無理して書かなくてもいいと思います。
(たとえば私の先輩は,「公認会計士の勉強してて,ゼミなんてやってる暇なかった。」と言っていましたし,大学在学中に合格していました。すごい…)
この考え方は「ゼミに入るかどうか」でも同じです。
ゼミに入るべきかどうかはこちら⬇️の記事で解説しています。
大学では「ゼミ」に入るべき?ゼミに入る意味・メリット・デメリットから考える
このような理由がなければ,書いた方がいいと思います。
「大変そう」とか,「自分に書けるか自信がない」という人も,ゼミの教員に指導してもらいながら書きますので,あまり心配しなくて大丈夫です。
ちなみに,「面倒くさいから」みたいな理由で書きたくないのであれば,卒論を書く4年次のゼミは履修しないでほしいと思います。
教員としても,そういう学生の指導はやりたくないですし,お互いにとってムダでしかありません。
お互い不幸になるだけですから,むしろ取らないでください…
大学の授業は(学生数が多い経済学部などでは特に),ほとんどが講義形式(教員が一方的に喋ることが多い形式)です。
講義形式の授業では,せいぜいレポートが課題として出されるくらいで,自分で研究したり,論文を書いたりする授業はほとんどありません。
ゼミとその集大成の卒業論文は貴重な機会です。
そして,この後説明するように,デメリットよりもメリットの方が多いので,ぜひ書くことを検討して欲しいです。
3.卒論を書くメリットと書かないデメリット
3-1.卒論を書くことで得られるもの(メリット)
まず,卒論を書くことで得られるメリットを挙げていきます。
すぐに思いつくものだけでもこれら⬇があります。
- 論理的思考力が身につく。
- 文章力が身につく。
- 柔軟な思考力が身につく。
- 就職,進学に有利になるケースがある。
- 自信がつく,達成感が得られる。
- 優秀論文のコンテストなどに応募できる。
卒業論文は「論理的に」書かなければいけません。
「自分はこう思います!」みたいに,自分の意見をただ書くだけでは成り立ちません。
たとえば,「卒論を書くべきか?」をテーマにしたこのブログ記事を,

私は書いた方がいいと思うよ。
書いた方が君のためだよ。
で終わらせたらどうですか?

え?理由は?
もっと詳しく説明してよ!
と私は読者の皆さんに怒られるはずです。
そりゃそうですよね。
もし理由を書いたとしても,

自分は書いてよかったと思ってるよ。
だから書いた方がいいと思うよ。
なんて理由だったら,やっぱり怒られますよね。
社会人になってからも,感情論で自分の言いたいことだけを言ってくる人は,,,(少なくとも仕事では)ほとんど相手にされないでしょう。
大事なことは,「こういうメリットがあるから」とか,「メリットがデメリットを上回るから」ということを具体的に説明することです。
読んでくれた人が「納得」してくれるかどうかは別として,少なくとも,「この人はこういう理屈でこう主張しているのね,言いたいことは分かるわ」と理解してもらうことが大切です。
当たり前のことのようですが,いきなりできるものではなくて,やっぱり訓練が必要になります。
卒論は,とってもいい訓練になります。
論理的な思考ができていたとしても,それを明確に読み手に伝えられる文章が書けなければいけません。

日本語の文章なんて書けないわけないでしょ?
バカにしてるの?
と思うかもしれません。
でも,いざレポートや論文を書こうとして,結構苦戦した経験があると思います。
私もそうでした(というか,今でも苦戦します…)
会話の場合にはある程度曖昧な表現でも相手に伝わったり,補足説明をして伝えることができます。
文章の場合は,書いてある文章を読んだ人が,その文章だけから書き手のあなたの言いたいことを理解してくれなければいけません。
卒論の場合は数万字の長い文章になりますから,長い文章を一貫して意味が通るように書く数少ない機会です。
ゼミの教員に大量の「赤ペン」を入れられることもあると思いますが,これも,文章の書き方を細かく指導される数少ない機会です。
自分が書いた文章を「赤だらけ」にされると嫌な気持ちになるのも分かります。
私も指導教授に「日本語がなってない」と赤だらけにされました。
ただ,私のゼミにいた学生が,以前こんなこと⬇を言っていました。

論文を書いていた時は辛かったですけど,就活でエントリーシートを書くときにすごく役に立ちました。
文章の細かい表現まで気にするクセがついたので,論文を書いていて本当に良かったです。
文章力は社会人になってからもずっと役立つスキルです。
雑な文章や論理的でない文章を書いてくる人は,「仕事できない人なのかな?」と思われたりもします。
逆にそこがしっかりしていれば「しっかりやってくれそうな人」と思ってもらえるはずです。
卒論は,すでに答えが出ているものではなく,答えのないものに取り組むものです。
もしくは,一般的に言われていることが間違ってるんだ!というパターンもあります。
いずれにしても,すでに整備された道を行くわけではありませんから,苦労しながら,色々な方法を試しながら,卒論を作り上げていくことになります。
1つのやり方で突破できるなら話は簡単なんですが,試行錯誤しながら色々な方法を試していくので,物事を柔軟に考える習慣がつくはずです。
世の中,「お勉強」のように答えが分かっていることなんてほとんどありませんから,とっても大事な力ですね。
卒論を書くことで,就職や進学に有利になる場合があります。
たとえば,一般的な就活の中でも,「どんなテーマで卒論を書いて(書こうとしていて),どんな結論を得たのか(得られそうなのか)。どんな苦労があって,どうやってそれを乗り越えたのか」の題材になります。
いわゆる「ガクチカ」の候補筆頭になります。
他にも,研究職や専門職を志望するならますます重要になります。
また,大学院への進学を考えているならほぼ間違いなく必須です(卒論を書かなかった,書けなかった学生が修士論文を書けるとは思ってもらえないでしょうし,大学院入試で必要になる研究計画も書けないでしょう)。
単純ですが,長い卒論を書き上げれば自信がつきます。
いい記念にもなります。
数年後に見たら恥ずかしくなることもありますが,それも含めていい経験です。
私も今自分の卒論を見たら色々と直したくなります(というか,丸々書き直したくなります(笑))。
逆に言えば,成長を感じられるいい材料でもあります。
大学・学部によっては卒業論文のコンテストのようなものが設定されているところがあります。
結構よくあるイメージです。
「自身の通っている大学名+優秀論文」などで検索してみると,過去の優秀論文を見ることができるかもしれません。
一度試してみてください。
優秀論文に選ばれれば,達成感も,優秀論文として認められた自信も得られます。
優秀論文には賞金が設定されていることもあるので,ちょっとしたご褒美がもらえることもあります。
3-2.卒論を書かないことで失うもの(デメリット)
次に,卒論を書かない場合に失うもの(得られなくなるもの)を挙げてみます。
基本的にはここまで解説してきたメリットが得られないことになります。
- 自分で調べる・考える・まとめるといった重要な訓練の機会が無くなる(減る)。
- 就活の自己RPのポイントや面接で話せるエピソードが減る。
- 就職先によっては不利になることもある。
これは社会人になってからも一番といっていいほど大切な力です。
社会人になってから,

あの人の文章って変だよね。
読んでも何言ってるか分からないんだよ。
とか

あの人って理屈が通じないから,理屈で話ができなくて困るよね。
なんて言われたら悲しいですよね。
昇進にだって関わってくるかもしれません。
仕事の幅も狭くなってしまうかもしれません。
卒論やゼミでの取組みは学生時代に力を入れたこと(ガクチカ)の代表例です。
これが使えなくなるので,その代わりになるものを見つけておかなければいけなくなります。
専門職を目指す場合には,卒論をしっかりと書いていた人とそうでない人とで差が出る可能性があります。
大学院への進学の場合には必須と言ってもいいレベルなので,大学院進学という選択自体ができなくなる可能性もあります。
4.卒論を書くデメリットと書かないメリット

逆に卒論を書くデメリットはないの?

基本的にはないね。
あえて言えば,時間が取られることくらいかな。
あとは書くのが大変だとかそのレベルの話だね。
基本的にデメリットはありません。
唯一といっていいデメリットは,はやりそれなりに時間が取られることです。
ですから,先ほど書いたように,「資格試験の勉強」や「起業して忙しい」といった場合にはそちらを優先してもらっていいと思います。
あとはたとえば,卒業単位がギリギリで卒論をやっていると他の科目の勉強時間が無くなって卒業できなくなってしまう!みたいなものであれば,仕方ないかなぁ,とも思います。
繰り返しですが,基本的にデメリットはありませんので,大変そうでもぜひ挑戦して欲しいです。
5.卒論を書きたくない,意味がないと思う学生へ

卒論って大変そうだし,必要ないならやっぱり書きたくないよ…
その気持ちも分かります。
ましてや,就職や卒業が決まっているなら「書かなくてよくない?」と思うのも普通のことかもしれません。
「書かなくてよくない?」となりそうな理由と,それに対する私なりの意見を書いてみたいと思います。
就活が順調に進んで内定がもらえていたら,先ほど解説した就職関連のメリットは意味がなくなります。
大学生→社会人という短いスパンでは,卒論は必要なさそうですね。
ただ,卒論で身につけられる力は,ここまで書いてきたように,社会人になってからも,というよりも,社会人になってからこそ役に立つものが多いです。
企画・プレゼン資料を論理的な流れが繋がるように,必要なデータなどを示しながら作る基本的な力,問題解決力,発想力,柔軟な考え方,などなど,たくさんあります。
卒業のために必要な単位が足りているのであれば,単位のために卒論を書く必要はありません。
それでも負担の大きい卒論の執筆をするのに気が進まないのはよく分かります。
ただ,これも先ほどと同じような理由ですが,卒論で身につけられる力は,その後社会人になってからとても役に立つものです。
卒業のための単位が足りているなら,それこそ,単位の心配をせずに卒論に取り組んで力を付けることができます。
大変そうだなということで悩むのは分からなくもありません。
卒論を最後まで書き上げることの負担は大きいです。
でも,ここまで説明してきたようなメリットがたくさんありますし,卒論は毎年書くものでもありません。
(基本的に,4年生の時に書くのが最初で最後,人生で1度きりです。)
せっかくの機会だから,と前向きに考えてみてほしいです。
繰り返しになりますが,単に「面倒くさい,ダルい,やりたくない,書くつもりもない」という場合には書かなくて大丈夫です。
無理に書かせてもお互いにいいことはありません。
6.よくある質問(FAQ)
最後に,卒論を書くかどうか迷っている学生向けに,いくつか想定される質問と回答をまとめてみました。
気になる物があれば見てみて下さい。
卒論は必ず書かないといけないの?
ものすごくざっくりとしたイメージは,このような⬇️感じです。
・国立大学→基本的に書く(書かせる)
・大規模な(人数の多い)私立大学→自由
・中・小規模の私立大学→基本的に書く(書かせる)
卒論を書かずに就職しても大丈夫?
卒論を書いていることを条件にしている企業はほとんどないと思います。
(専門職では多少差が出る可能性があり,大学院進学ではほぼ必須です。)
ただ,卒論を書くことによって身につく力の差は出てくると思います。
就活と卒論の両立はできる?
「卒業単位がぎりぎりで,4年生で授業を取りまくってる!1つでも落としたら終わる…」みたいな状態でなければ全然問題ありません。
卒論指導はそれぞれの学生の進度や就活の状況をある程度考慮してくれることも多いので,指導教員に相談しながら進めれば大丈夫です。
「先生,今週と来週は就活が佳境で!終わってから頑張りますので許してください!」といえば普通は問題ありません。
安心してください。
卒論の字数ってどのくらい?
文字数の指定がされている大学・学部もあれば,指定されていない大学・学部もあります。
大学や学部では指定されていないものの,ゼミの担当教員が独自に設定している場合もあったりします。
指定されている場合にはそれに従うしかありません。
私が卒論を書いた時は特に指定されていませんでしたし,自分でも指定していません。
そのうえで,ざっくりと目安の文字数をお伝えしておくと,2万字くらいかなぁという印象です。
Wordを40×40で作成した場合,図表も含めてざっくり15~20ページくらいですね。
1万字だと少ないかなぁ,3万字だとそこまではもとめなくていいかなぁ,という感じです。
2万字というとものすごく多いイメージがあると思いますが,この記事のここの部分までで7千字近くあります(書きすぎですかね…読んでくれているのかな…)。
そう考えると,それほどとんでもない量ではないと思ってくれる??かな??と。
できれば卒論を書きたいけど,もし無理だったら途中で諦めてもいいの?
頑張ってやってみたけどやっぱりダメだった!ということもたしかにあり得ます。
そんな時は(卒業に問題がないことを確認してから)担当教員に相談してみてください。
実際にそういう学生もいます。
でもそれは仕方ないことですね。
もし最後まで書き上げられなかったとしても,それは1つの経験になります。
ただし,いきなり諦めるのではなくて,その前の段階でゼミの先生に相談をして,できることはやって,それでもダメだったら諦めるのもアリです。
卒論のテーマはどうやって決めればいいの?途中で変えてもいいの?
卒論のテーマの決め方については別記事で詳しく解説しようと思います。
ただ,基本的には自分のやりたいこと(好きなこと,趣味に関連すること)や今後に関係すること(就職先の業種,就活で目指している業界など)にすることをお勧めします。
自分に関係することでないとモチベーションの維持が難しかったりしますし,これらのことは一定の知識があるので取り掛かりやすくなります。
そもそも,卒論とレポートはどう違うの?
論文とレポートの違いは,「独自性」や「新規性」があるかどうかです。
「一生懸命調べてまとめました」,というだけでは「レポート」であって「論文」にはなりません。
論文とレポートの違いはこちら⬇️の記事で詳しく解説しているので,ぜひ読んでみてください。
卒論に取り組む前に知っておきたい「論文」と「レポート」のたった1つの違い
まとめ
卒論を書くべきかどうか,卒論を書くメリットとデメリットについて解説してきました。
エッセンスをまとめておきます。
- 卒論は書いた方がいい。なぜなら,
- 論理的思考力や文章力が身につくし,自信もつく。
- 就活でのアピールポイントになる。
- 大学院進学では必須。
- 卒論を書くデメリットはほとんどないうえに,メリット>デメリット。
「卒論は大変そう」
そう思って躊躇する気持ちも分かりますが,研究者(大学教員)からほぼマンツーマンで研究指導をしてもらえる数少ない機会でもあります。
一緒に卒論に取り組む友達がいればいい刺激にもなりますし思い出にもなります。
どうしても無理だったら諦めてもいいので,ぜひ,卒論には取り組んでみてほしいと思います。
その他適宜追加します。