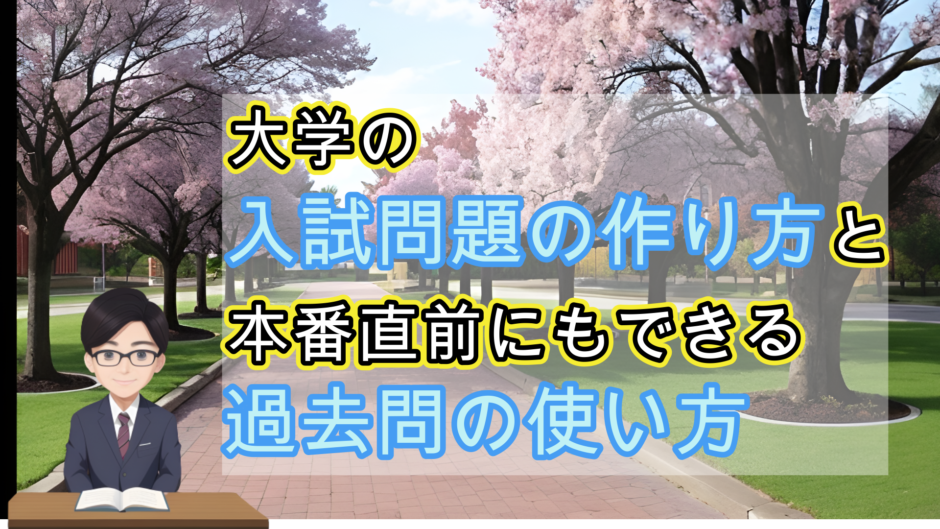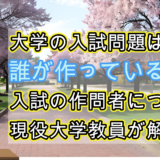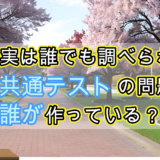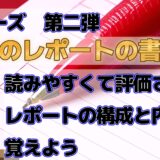・大学の入試問題はどのように作られているのか。
・大学入試の過去問の使い方。

現役大学教員(私立大学,経済学部)
学生と接する中で伝えたいたくさんのことをブログ(サードゼミブログ)で発信中。
入試問題の作成も複数回担当。

大学の入試問題ってどんな風に作っているの?🤔
気になりますよね(笑)
入試問題は基本的にその大学の教員が作ります。
「誰が入試問題を作るのか?」についてはこちらの記事(大学の入試問題は誰が作成している?入試の作問者について現役大学教員が解説)をご覧ください。
大学の入試問題の作り方やこだわりは,大学によって,科目によって,担当者によって色々と違いがあると思います。
ここでは,これまで複数回,複数の科目の入試問題を作った経験などを踏まえて書いていきたいと思います。
なお,この記事で書いているのは大学内で入試問題を作っている私立大学を想定しています。
この記事を読んでもらえれば,入試問題の作り方や流れというのが分かります。
入試問題の作り方が分かると過去問の使い方のヒントにもなったりしますので,ぜひご覧ください。
1.入試問題を作る手順
早速入試問題の作問の流れを見てみましょう。
大学や科目によって違いがあると思いますので,あくまでも基本的な流れです。
- 全体の方針を決める。
- 各自作問。
- 作問したものを持ち寄って検討。
- 検討結果を受けて修正(複数回繰り返す)。
- 点検,コメント
- 点検結果,コメントを受けて協議,修正(複数回繰り返す)。
①まずは,分担を決めたり,出題範囲を決めたり,難易度のすり合わせをしたり,といった作業をします。
各自が作った問題が被っていたり,出題範囲外だったりすると無駄な作業になってしまいますからね。
②次に,その方針に基づいてそれぞれ問題を作ります。
③作った問題を持ち寄って検討をしますが,その時に確認するのはこれら⬇のポイントです。
- 問題が重複していないか。
(社会系科目とかだと他科目との重複も考慮しなければならないこともあります。) - 出題範囲に入っているか。
- 出典の確認。
(該当する教科書の記述,資料集,新聞記事など) - 正答は1つに導けるか,別解はあるか。
- 難易度は適切か。
初回の段階では出題範囲や出典の確認をしっかりします。
この時点ではまだ粗削りになるのは当然ですし,問題の差し替えなんかもそれなりにあります。
④検討結果をそれぞれが持ち帰り,それを反映させて問題を修正します。
修正したものを再び持ち寄って検討をすることになります。
2回目以降では,正答がしっかり導けるかどうか,文章の表現に問題はないかといったところを細かく詰めていく感じです。
これを複数回繰り返して,第1段の原案を作ります。
ここまでの作業は作問チームの作業です。
⑤作問チームの中である程度「これでいいのではないか」という所まで持って行くと,次に作問担当とは別の教員が「点検」をします。
この作業は基本的に学内の教員が担当しますが,場合によっては予備校などの外部業者に依頼するケースもあるようです。
ちなみに,作問者と点検者はお互いに誰か分からないようにはなっています。
(実際にはある程度予想がついてしまったりしますが,建前としては,です。)
⑤この点検チームのコメントを受けて,作問チームが問題の修正をします。
コメントには的外れなものもあったりしますので,必ずしもすべてその通りに対応するわけではありません。
作問チームで協議して,作問チームの方針を決めていきます。
この後,再び点検をして修正という作業を繰り返して,最終的な問題が完成します。
何回くらいこの作業を繰り返すかについては,大学,科目によって違ってくると思います。
とはいえ,最低でも2,3階はやるはずですね。
2.入試問題の作問で意識すること

入試問題を作る時にはどんなところに重点を置いているの?
入試問題を作るのは結構神経を使います。
気をつけることはいくつかありますが,並べてみるとこのくらい⬇でしょうか。
- 正答が導けること。
- 出典の確認。
- 難易度が適切か。
- 過去問との重複はないか。
- 各個人のこだわり。
これは当然ですね。
答えが1つに決まらなければ出題ミスになってしまいます。
しかし,これって意外と大変なんですよ。
たとえば,教科書に書いてある記述が間違っているとか,間違っているとまでは言えなくても適切でないものなんていくらでもあります(主に社会系の科目ですね)。
高校の学習実態に合っていないと「悪問」になってしまう可能性もあります。
これも基本的なことですが,基本的には「教科書に記述があること」です。
教科書で学習している範囲から問題を出さないと,「解けない」問題になってしまいますからね。
ただ,もちろん全社の教科書に載っていなければならないというわけではありません。
そんなことをしていたら出せるところなんてほとんどなくなってしまいます。
大学や科目ごとに「出題していい基準」があると思います。
1社だけでも載っていればいいのか,複数社必要なのか,などの基準ですね。
資料集や用語集など,教科書以外の教材については微妙なところです。
資料集に載ってるならOK,というところもありますし,教科書に載っていないならNGというところもあるはずです。
教科書以外では,新聞記事などを根拠とした「時事問題」もあります(これも主に社会系の科目ですね)。
時事問題でも大学や科目ごとに「出題していい基準」があるはずです。
全国紙複数社に載った,などですね。
出題時期についても基準があると思います。
極端な例ですが,10年前のことを「時事問題」と言われても「は?」となってしまいます。
直近1年とか2年とか,あるいは,受験生が高校生になって以降のこと,といった感じです。
これはその大学のレベル,大学の欲する学生のレベルに合わせて作ります。
全国の大学が東大生に求めるようなレベルの問題を作っていては意味がありません。
ある程度適切な難易度にしないと,点数が固まってしまって線引きが出来なくなってしまいます。
基本的にはやはり「教科書に載っている範囲」でしょう。
それと,人によるところはありますが,個人的には比較的簡単なものと難しいものを混ぜるようにしています。
している,というより,結果的にそうなる,と言った方が適切かもしれません。
すべて同じ難易度で作るなんて無理ですし,受験生の学力を点数に反映させようと思うとある程度難易度が違うものが混ざっている方がいいですからね。
入試問題を作る時には,最低でも直近1,2年分くらいの過去問は確認します。
そこで出されている問題があれば,同じものは出さないようにすることが多いです。
数学などでは判断が難しいかもしれませんが,社会系や理科系だと結構分かりやすいかもしれません。
その他,作問を担当する人によってこだわりがあったりしますね。
たとえば,
- 暗記系の一問一答は好きじゃないから,考えさせる問題を作りたい。
- 教科書では重視されてないけど,実は大事だからここを出すか。
- 教科書の内容に問題があるから,正しい理解を求める問題を出すか。
- 一問一答が一番ラクだな。
(これを「こだわり」というのは不適切かもしれませんが。)
といった感じです。
一問一答というか,単純な暗記系の知識問題は,,,私は嫌いです。
もちろん,全く入れないというわけではありませんが,考えて解いてもらう問題を作りたいタイプです。
もちろん,一問一答形式を作る人もいるので,結果的にバランスが取れれば良いですが,全部一問一答で作ってくるみたいな人がいて,正直何だかなぁ,と思ったりします。
一問一答は作るのがラクなんですよ。
文章中に空欄を作って書かせるか選ばせるかをすればいいので。
ラクしているのが許せないとか,そういうことではなくて,もう少しちゃんと問題作りましょうよ,,,とは思います。
ただ,作問は常に人手不足なのでそうも言っていられないという悲しい現状があります…
こうした作問者のこだわりは人によって違うので,各問題の特徴にもなります。
一方で,担当者が毎年変わるので,年によるブレにもなります。
あとは,正答を導くのに影響がなかったり,特定の政治的メッセージなどが無ければ「変わった問題」や「変わった題材」というものをやってもOKです。
私もちょくちょくやります。
個人的な感覚ですが,

この仕事やらさせてるんだからちょっとくらい問題で遊ばせてくれ。
という感じでやっています。
軽いもので言えば登場人物の名前を趣味に寄せてみるとか,状況設定のところで皮肉を入れてみたりとか,気付きづらいとは思いますが,よく見ると結構色んなこだわりがあって面白いと思います(笑)
3.過去問の利用方法
さて,入試問題作成の手順と作問で意識することを書いてきましたが,その中で,「過去問と被らないようにする」というのがあったと思います。
これを考えると,過去問って結構大きな情報になると思いませんか?
つまり,前回,前々回くらいの入試で出たところは,全く同じものはほとんど出題されないということです。
(絶対というものではありません。あくまで傾向として,です。)
過去問と言えば,
- 出題方法,難易度,問題量などの確認。傾向を掴む。
→その大学の形式に慣れる,戦略(時間配分や解く順番など)を立てる。 - 自分の位置の確認。
→得点率と合格ラインの確認。
といった利用方法がメインだと思います。
しかし,これに加えて,
直近で出題されたところ以外がメインターゲットになる。
という予測ができます。
ある意味で,「ヤマを張る」ための情報も入っているということです。
ヤマを張るというのは,最後の最後,時間のない中での追い込みなどでやるくらいではありますが。
学力が同じであれば,その大学の出題方式や傾向に慣れている受験生や,出題される可能性が高いところに集中した受験生の方が合格しやすいでしょう。
純粋な学力以外の部分の小さな差が結果を分けることもあると思いますので,使える情報は有効活用しましょう。
4.教員が作問で苦労すること

問題を作っていて大変なのはどういうところなの?
もちろん「作問の負担」というのはあります。
「やりたくねぇ」とか「面倒くさい」とか「時間が取られる」とか,そういったものですが,これはまぁ仕方ないので置いておきましょう。
個人的には,

どこを出すか?
出すところが無ぇ!
というのが一番困るところです。
問題のアイデアは無限に湧き出てくるものではありません。
ここまでの内容を思い出してみて下さい。
- ほかの作問者(場合によっては他科目)と被っちゃいけない。
- 去年,一昨年の問題とも被っちゃいけない。
- 教科書にある内容から出すのが基本。
この条件がすべて達成されるところって,あんまり多くないと思いませんか?
しかも,自分がある程度内容に詳しいところから出したいわけです。
教科書に載っている内容も意外と多くありません。
つまり,この制限の中からいくつも問題を作るというのは,

本当に出すところが無ぇ!!
という状態によくなるということです。
他の教員と話していても,「何出すかなぁ…出すとこないですよ…」みたいな会話も多いです。
受験生の皆さんは,

何が出てくるか分からない!
範囲が広すぎる!
と思うかもしれませんが,意外や意外!問題として出せるところってあんまり多くないな,というのが入試問題を作ってみての私の感想です。
そう考えると,「意外と問題として出される範囲って狭いんだよ」ということを知って貰えたらなと思います。
(もちろん,具体的にどうということまでは書けずに申し訳ないのですが…)
まとめ
以上,私立大学の場合の入試問題の作り方の流れと過去問の利用方法について解説してきました。
簡単にまとめておきましょう。
- 作問の流れは,全体方針→作問→検討,修正→点検→修正。
- 特に意識するのは,
・正答が間違いなく導ける。
・教科書の範囲である。
・過去問と重複しない。 - 過去問は傾向を知るだけでなく,ヤマを張ることにも使える。
- 作問者は意外にも出すところが少なくて苦労している。
入試問題の作成というのは,外からは分からないうえにブラックボックスなので色々な憶測が飛び交っていたりします。
ただ,実際には割とシンプルな,基本に忠実な作業がされているだけだったりします。
出題者の気持ちが少しでも垣間見えるようになってもらえたら,双方にとって良いことだと思います。
それでは最後まで読んでいただきありがとうございました。
その他,適宜追加します。