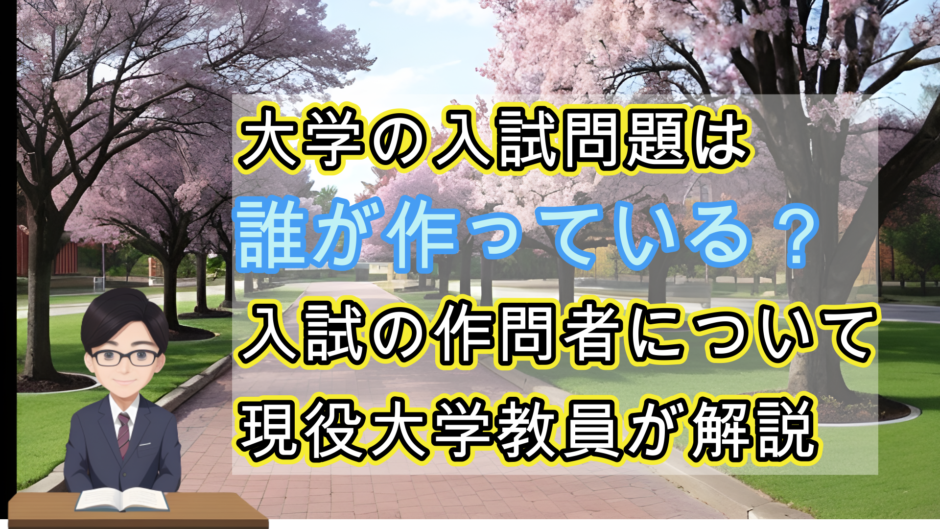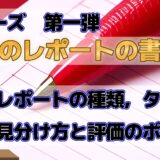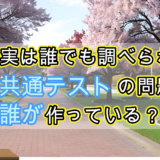・大学の入試問題は誰が作っているのか

現役大学教員(私立大学,経済学部)
学生と接する中で伝えたいたくさんのことをブログ(サードゼミブログ)で発信中。
入試問題の作問も複数回担当。

大学の入試問題って誰が作っているんだろう?🤔
受験生にとって「入試問題」はとっても関心のあるものですよね。
色々な疑問があると思いますが,この記事では「入試問題って誰が作っているの?」というシンプルな疑問にお答えします。
この記事を読んでもらえれば,入試問題を誰が作っているのか,それによって入試問題の傾向等にどのような影響があるのかを知ることができます。
この記事の内容は基本的に「私大」の入試問題(一般入試)について書いたものです。
「外注」などの内容は国公立大学には当てはまらないと思いますので,ご注意ください。
入試問題の作成は,外からは完全に「ブラックボックス」となっていると思いますので,気軽な読み物として楽しんでいただければと思います。
1.大学の入試問題を作る2つのパターン
大学の入試問題を「どこが(誰が)作るのか」という質問に対する答えには2つのパターンがあります。
- 学内で作る。
- 外部で作る(=外注する)。
入試問題の情報は外に漏れてはいけませんから,通常は大学内部で作ります。
「学内で作るとすれば誰が作るのか?」と考えれば,普通に考えて教員(大学教員)が作問をします。
大学の事務の方が作るという訳にはいかないですし,消去法でもやはり教員ということになります。
とはいえ,すべての大学(私大の場合)が「自前で」入試問題を作るのかといえば,必ずしもそうとは言えません。
自前で作らない場合は,外部の業者に「うちの入試問題を作ってくれ」と依頼することになります。
実際に外注しているという大学の教員に会ったことはないので実態については分からないのですが,存在するというのは事実のようです。
文科省によるこちらの資料(「大学入学者選抜関連基礎資料集第4分冊(制度概要及びデータ集関係)」の73ページに,少し古いですが2007年度入試の外注状況がまとめられています。
https://www.mext.go.jp/content/20210330-mxt_daigakuc02-000013827_9.pdf)
実際に「入試問題制作」とか「入試問題作成代行」といった単語で検索をすると,いくつもヒットします。
外注している大学については知らないのですが,「うちの大学でも外注化を検討してるよ」という話は複数聞きます。
全国的に名の知れているような有名大学でも外注の検討をしていると聞きました。
現時点では,学内で(=自分の大学で)作るのが基本パターンになっています。
2.大学内で入試問題を作る場合
2-1.入試問題を作るのは専任教員
先ほどもお伝えしたように,それぞれの大学で入試問題を作る場合,担当するのは大学の教員です。
というか,教員以外にはいません。
これは何となく予想できていると思いますし,一般的に知られていることかもしれません。
となると次に気になるのは,

具体的にはどの先生が作っているの?🤔
ということだと思います。
大学で授業をしているすべての教員が担当しているかと言えば,そうではありません。
厳密にいえば,「専任教員」が担当します。
具体的には,
- 教授
- 准教授
- 講師(専任講師)
が担当します。
「非常勤の先生」,「助教」,「特任教授」といった人たちは基本的に問題作成に携わりません。
専任教員って何?職位の違いを知りたいという方ははこちら⬇の記事をご覧ください。
教授,准教授,講師,助教,何が違う?どう違う?大学教員の職位について解説
ちなみに,「ネットで検索したらなんて書かれているんだろう?」と思ってググってみたところ,「教授だけが担当している」と書かれたものもありしました。
しかし,これは嘘ですね。
教授だけではなく,准教授や講師もこの仕事に駆り出されます(笑)
なぜそう言えるかと言えば,
- 実際に私も,私の知り合いの准教授や教授も駆り出されている。
- 教授だけでは絶対に人手が足りない。
- むしろ若い教員の方がそつなくこなす(個人的意見)。
という理由があります。
入試問題を作るためにはかなりの人手が必要になります。
教授だけでは回りません。
それと,単純な一問一答を作るわけではない場合が多いので,そのあたりはむしろ若い教員の方が柔軟に対応して問題を作る傾向にあると思います。
2-2.誰がどの科目の問題を作るのか?
「入試問題の作成を担当する教員がそれぞれどの科目を担当するのか?」という疑問もあるかと思います。
これは大学の外部からはまず分かりません。
そして,一応大学内部でも,建前としては分からないようになっています。
分かってしまうと,問題を作る人と問題の点検(指摘)をする人の間でイザコザになることもあり得ます。
これは単純に困ります。
その予防もありますし,公平な目で問題を見てもらう必要があります。
もちろん,情報が漏れないようにという意味もあります。
ただ,実際には「あの人の専門ならあの科目だよね」とある程度の予想はできますし,出題者同士で顔を合わせることもあるので分かることもあります。
お互いに「先生は何の科目ですか?」なんて話をすることもありますので,その大学に数年もいればある程度分かるようになります。
出題者を決める入試委員などであれば,全体を把握する立場にあります。
もちろん,外部に漏らすようなことはありませんので,あくまでも内部,もっと言えば委員会レベルの範囲に限られる情報です。
もし大学の外で話をする時には,何の話をしているのか分からないようにして話しますね。
ちなみに,「あるある」かどうか分かりませんが,大学教員が「秘密の仕事」とか言った場合は入試関係の仕事(作問や採点)であることが多いです(笑)
2-3.学内で作った入試問題の特徴
これは大学ごとに事情が違うので何とも言えないのですが,一般的にはこれら⬇のものが見られることが多いです。
- 大学ごと,科目ごとの特徴が出やすい。
- 出題者によって癖があったり,形式が違ったりする。
- 出題範囲(出題箇所)も出題者の専門や関心によって偏る。
- 年によって傾向が変わったりする(毎年同じ人が作るわけではないから)。
大学の内部で作成するので,大学ごとに問題の作り方,出題傾向,出題形式などが違ってきます。
科目ごとでも違いが出やすいです。
(大学によっては,科目間でも統一するようにしているところもあるかもしれませんが,そこまでの労力を掛けられる大学は少ないと思います。)
そして,出題者によって問題の形式や出題範囲が違ったりします。
出題箇所が被らないようには調整しますが,その中で具体的にどのあたりの問題を出すのかは出題者に一任されることが多いです。
(もちろん大学や科目ごとに色々な「基準,ルール」があるはずですが,例も含めてこれはさすがに書けません…)
「大問1と大問2で全然問題の形式が違うんだけど…」(たとえば,大問1は一問一答の暗記系がほとんどなのに,大問2は時事問題と思考問題が多くてページ数も全然違う)なんていう場合は,大問1と大問2で出題者が違う場合が多いということですね(笑)
もちろん,ある程度形式の統一はしようとするのですが,入試問題の作成に掛けられる時間がたっぷりとあるわけではないので,どうしても限界があります。
また,「一問一答ばっかりじゃなくて考える問題を出せよ!」と思ったとしても,他の教員にそれを強要するのは無理です。
「文句があるならやらん」とか「だったらお前が作れ」なんて言われたら最悪ですからね…
問題を作る教員によって違いがあるということは,年によって問題の形式や傾向が変わりやすくなるということでもあります。
数年(あるいは長年)続けて問題を作る人もいますが,基本的には出題者の一部を入れ替えていくのが理想です。
作る人が変われば,問題も変わります。
これは「安定していないので対策がしづらい」とも言えますし「過去問で苦手な形式があったりしても,変わればチャンスがある」とも言えます。
3.大学外で入試問題を作る場合
3-1.誰が入試問題を作るのか?
大学が入試問題の作成を外注する場合,その問題を作る有力候補は予備校でしょう。
実際に外注しているという大学の教員に会ったことはありませんが,外注を検討している,あるいは外注の検討を進めているという話は複数聞きました。
全国的に名の知れた有名大学や,地方の有力大学でもそのような話を聞きました。

どうして外注しようとするの?
問題が漏れたりしないの?
入試問題みたいな大事なものを自分たちで作らないのってどうなの?
当然の疑問だと思います。
ということで,「なぜ外注しようとするのか?」を解説していきます。
3-2.入試問題の作成を外注する理由
大学が入試問題の作成を外注しようする理由はいくつかあります。
代表的なものとしては,
- 大学教員は高校教育については素人。
- 単純に人手不足。
- 入試問題作成の業務は負担が大きい。
といったものがあります。
これは分かりやすいですね。
我々大学教員は,実際に高校の現場でどのように教えているのかといったことは全く知らない人がほとんどです。
こちらの記事⬇でも少し書きましたが,大学教員は学生から見れば同じく「先生」でも,高校までの先生とは違って教員免許は不要です。
大学教員,大学教授には変わり者が多い?現役大学教員がその理由を考えてみた
ましてや高校教育の現場のことは分かりませんので,高校の教育現場との「ズレ」というのは必ず発生します。
もちろん,高校の現場のやり方が正しいかと言えば必ずしもそうではないでしょうが,受験生は困惑することでしょう。
大学の入試問題には,「このレベルのことは知っていて欲しい」とか,「こういう力を身につけていて欲しい」といった一定のメッセージは込められているかもしれません。
しかし,現場とのズレがあまり大きいのは望ましくないですよね。
はい,非常に単純ですが深刻な問題です。
入試問題を作るためにはかなりの人手が必要です。
- 作問者(科目ごとに複数)
- 点検者(科目ごとに複数)
- 全体の取りまとめや運営(主に入試委員)
問題を作ることも1人ではできません。
作問の段階で相互に誤りがないかをチェックしながら作ります。
問題の点検をする人も複数必要です。
これらをすべての科目について用意しなければいけません。
例えば単純に,国語,英語,数学,地理,日本史,世界史,政経,物理,化学,生物,地学の11科目で10人ずつ(作問者+点検者)必要だとすれば,それだけで110人の教員が必要になります。
小規模な大学では出題者の確保だけで厳しいですし,中規模大学,大規模大学でも決して軽い負担ではありません。
さらに,子どもが受験生の年齢だったりすれば作問や点検は担当できません。
学部長などは担当しないのが普通でしょう。
こうなると,ますます人手不足が深刻です。
入試問題の作成業務は「テキトー」にやるわけにはいきません。
出題ミスなどがあれば大変ですし,非常に神経を使います。
ですから,「1日だけ作業してハイ完成!」とはなりません。
複数回の点検と修正を繰り返して進めていきます。
こういう業務ですし,「引き受けてくれない人」っていうのがやっぱりいるんですよ…
あと,「お願いできない人」もいます。
(たとえば,仕事がテキトー過ぎて任せられない,過去に作問関係で問題を起こした,などなど)
ただでさえ人手が足りないのに引き受けてくれない,お願いする方も疲れる,お願いできない人もいる,,,かなり厳しい業務だということが分かってもらえると思います。
しかし,実際にはこうした事情にも関わらず外注化はあまり進んでいません。
大学内で入試問題を作っているところが多いです。
その理由を解説していきましょう。
3-4.外注化が進まない理由
外注化が進まない理由として,4つほどの理由が考えられます。
- お金。
- どのような学生を求めるのかに合わせた入試問題を作るべきという意見。
- 機密性の確保。
- 文科省による「自分で作れ」という姿勢。
これは非常に単純で,外注するとかなりのお金が掛かるはずです。
そりゃあそうですよね(笑)
入試問題なんていう大事なものを作るわけですし,十分な質が要求されるわけですから,安い金額でできるわけがありません。
大学の経営サイドから見れば,「教員にやらせた方が安上がり」ということになります。
求める学生像に合わせて入試問題を作るべきだという考え方です。
一定の理解はできますが,個人的には,

言いたいことは分かるけど,全部の科目でこれをやらなければならないのか?
そのあたりも含めて外注先に伝えるのもアリでは?
と思います。
入試問題が外に漏れては大問題ですので,外注というとそのあたりが心配されることもあります。
とはいえ,しっかりした企業であればこのあたりの心配はあまりないのだろうとは思います。
先ほどリンクを載せた文科省の資料(「大学入学者選抜関連基礎資料集第4分冊(制度概要及びデータ集関係))に次のように書かれています。
「試験問題の作成は,各大学の受け入れ方針に基づき,各大学が自ら行うことを基本とすること。」
「外部の機関等に試験問題の作成を行わせることは,大学入学者選抜の機密性や公平性,中立性の確保の観点から,社会的な疑念を招くおそれがあり好ましくないことから,慎重に対応すること。」https://www.mext.go.jp/content/20210330-mxt_daigakuc02-000013827_9.pdf)
「基本とする」とか「慎重に対応」といった表現であって「ダメ」とは書かれていませんが,「自分たちで作れ!」という基本姿勢は十分伝わりますね。
こういった事情で,外注かはなかなか進まないというのが現状です。
4.教員のホンネは「入試問題は作りたくない」

先生たちは入試問題を作る仕事についてはどう思っているの?

もうね,やりたくないね。
やらないで済むなら絶対やらないよ。
これです(笑)
全員がそうだとまでは言いません。
中には,楽しんで作っている人もいるかもしれません。
ただ,大部分の教員は「マジやりたくねぇ~」と思っているはずです。
その理由は,主に3つあります。
- 外入試業務は学内業務の1つの雑務。
- 入試業務の報酬安すぎ問題。
- 高校教育については素人で本当に分からない。
順番に説明していきます。
大学教員の業務は,優先順位をつければ,
- 1.研究(論文を書く)
- 2.教育(ゼミの指導,講義)
- 3.学内業務(◯◯委員,入試業務,など)
となります。
(大学教員の業務についてはいずれ別記事にしようと思います。)
入試業務というのは大学教員にとっては優先順位の高い仕事ではありません。
受験生からすれば怒りたくなるかもしれませんが,入試問題を作るというのは大学教員にとっては「雑務」なんです。

入試問題を作ったらどのくらいお金がもらえるの?
結構儲かるの?
入試問題の作問と言えば世間的にはかなり大きな仕事なので,結構な金額がもらえると思うかもしれません。
(あるいは,業務のうちなんだから別に手当が出ること自体がおかしいという意見もあるかもしれませんが。)
実際のところは,入試問題を作る仕事をすると手当がもらえるのが普通です。
しかし,,,その手当は安いです!!
具体的なデータを持っているわけではないですが,知り合いの教員に話を聞いていたりする限り,平均的には数万円程度ではないかと思います。
10万円もらえれば,「いいじゃないですか」と言われるイメージです。
酷い大学になると数千円,一番ひどいのは「もらえるだけいいじゃないですか」と言っていた先生がいたことです…
(ちなみに,噂レベルではかなりの金額がもらえる大学もあると聞いたことがありますが,すみません,これは確認できていません。)
かつて,受験生がたくさんいたころは入試手当も大盤振る舞いだったと聞いたこともあります。
しかし,今も,そして今後も受験生は減っていく一方です。
受験生減少→受験料収入減少→手当減少の流れが今後も続きます。
場合によっては,大学自体が「潰れて無くなる」かもしれません。
入試問題を作るのはかなり神経を使いますし,時間もかかります。
作問だけでなく,作問を担当すれば当然試験当日は本部で待機,採点も担当しなければいけません。
それに対して数万円,,,しかも雑務…
何となく「やりたくねぇ…」と言いたくなる気持ちが伝わりましたでしょうか。
(プチ情報というか,詳しくは改めて別記事にする予定ですが,「共通テスト」の作問に対する報酬も安いです…)
そして,先ほども書いたように,大学教員は高校教育については素人です。
自分が受験していない科目の作問を担当しなければいけないこともあります。
そうなるとレベル感も分かりませんし(作ってみた問題の「高校生から見た難易度」が分からない),下手をすると「難問」や「奇問」といった扱いの問題となってしまうこともあり得ます。
このように,自分たちが全く素人の分野でしかも時間もかかる雑務扱いの仕事を,安い報酬でやらなければならない,というのが大学教員にとっての「入試問題作成業務」なんです。
5.推薦入試,総合型選抜の作問
推薦入試や総合型選抜で筆記試験や小論文試験の問題も教員が作成します。
推薦入試や総合型の問題は,基本的には学部ごとに作ります。
各学部から数名程度が駆り出されて作問をすることになります。
推薦入試や総合型選抜の問題は,一般入試に比べて負担が軽いです。
その理由としては,
- 作問に関わる人数が少ない。
- 記述試験や小論文試験であれば問題数が少ない。
といったあたりです。
ちなみに,推薦入試や総合型選抜の作問については,手当は出ないか,出たとしてもかなり安いと思います。
私は貰った記憶がありません。
(あるいは,もらっていたことに気づいていないレベル=2000円とかではないかと思います。)
まとめ
大学の入試問題はだれが作っているのか?について解説してきました。
内容を簡単にまとめておきましょう。
- 入試問題を作るのは大学の専任教員。
- 外注している大学もあるらしい。
- 大学教員としては入試問題の作成はできればやりたくない。
大学の入試関連のことは,なかなか外部には出てこないので,「へぇ~」と読んでもらえたらありがたいです。
それでは最後まで読んでいただきありがとうございました。
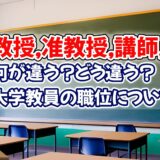 教授,准教授,講師,助教,何が違う?どう違う?大学教員の職位について解説
教授,准教授,講師,助教,何が違う?どう違う?大学教員の職位について解説
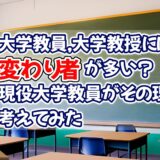 大学教員,大学教授には変わり者が多い?現役大学教員がその理由を考えてみた
大学教員,大学教授には変わり者が多い?現役大学教員がその理由を考えてみた
その他適宜追加します。